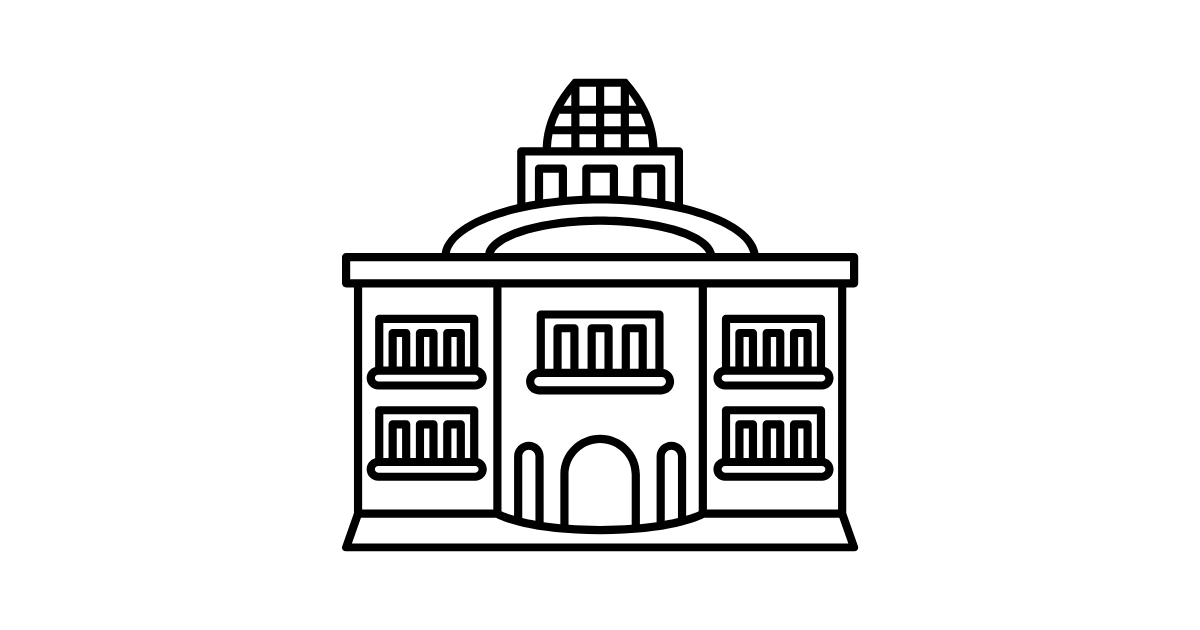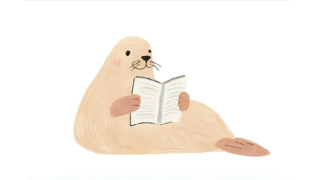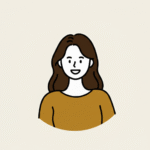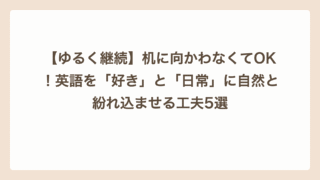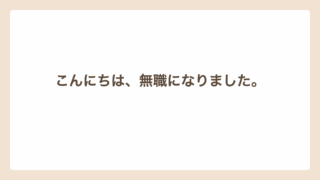こんにちは、さちこです。
日本ではここ数日、政治面で大きな動きがあり、ニュースに注目しているところですが、ふとオランダの政治はどんなものなのだろうと気になって調べてみました。
オランダは、ヨーロッパの中でも特に合意を重んじる国として知られています。政治体制は立憲君主制ですが、実際の政治運営は議会を中心とした民主主義です。オランダには十を超える政党があり、単独で過半数を取る政党は存在しません。そのため、政府は常に連立によって成り立っています。
オランダの政治は「合意」が前提
この連立の文化は、単なる政治技術ではなく、オランダ社会全体の価値観と深く結びついています。宗教、地域、階層、思想といった多様な背景をもつ人々が共存するために、オランダ人は歴史的に話し合うことを重んじてきました。この姿勢を象徴する言葉がポルダー・モデルです。
ポルダーモデルは、雇用者団体・労働組合・政府が協力する合意形成の方法であり、1980年代のワッセナール合意が重要な転機となりました(Wikipediaより)。干拓地(ポルダー)を守るために、立場の違う人々が協力せざるを得なかったという歴史的背景が、合意形成を尊ぶ文化を育てたと理解されています。
ヨーロッパにおけるオランダの独自性
ヨーロッパ全体を見渡すと、この「合意型政治」は例外的です。フランスは大統領制でリーダーが強い権限をもち、イギリスは二大政党制で政権交代が明確です。ドイツも連立は多いものの、官僚機構が政策形成に強く影響します。
その中でオランダは、議論の場で少数派の意見も丁寧に扱い、合意に達するまで時間をかけます。効率は悪く見えるかもしれませんが、その分、決まった政策には広い支持が得られ、実行力も高い。社会的な信頼が制度を支えていることも、統計や政治分析から確認されています(Election Guide, 2023)。
教育と市民文化が支える民主主義
オランダでは、子どもの頃から自分の意見を言う練習が重視されます。この習慣は成人後の市民参加にもつながります。「政治は特別な人が行うものではなく、市民の集合的な意思決定である」という感覚が社会全体に浸透しています。地方自治体が市民から意見を募ることも一般的で、政治が生活に自然に溶け込んでいることが数字や教育制度からも裏付けられます。
日本との違い
日本の政治文化を思い返すと、意見の違いをあえて避ける傾向があります。オランダでは、意見が異なることは前提であり、それを話し合うこと自体が成熟した社会の証とみなされます。議論を通じて共通理解を作る文化は、日本に比べて政治が生活により近いことを示しています。
政治は誰かがやってくれるものではない
オランダでは政府は「すべてを解決してくれる存在」ではなく、調整役です。市民は自分たちで課題を話し合い、地域で解決する文化をもっています。この文化が、社会的信頼や市民参加を支え、政策の実効性を高めることも、現地の調査結果で裏付けられています。
もちろん、完璧ではありません。連立交渉は長期化しやすく、政策決定が遅れることもあります。しかし、多様な声を調和させる姿勢こそが、オランダ政治の本質です。
おわりに
私は投票権を持たない立場として、オランダの政治を外から観察することになりますが、その距離感がむしろ面白く感じられます。合意を重んじる政治は、一見穏やかに見えて、非常に高度な民主主義のかたちです。政治が生活の中に自然に存在するオランダの社会は、議論の成熟と市民参加の実践が日常に溶け込む、現代民主主義のモデルとも言えるでしょう。
参考文献
- Dutch Government Collapses After Right-Wing Leader Wilders Walks Out
- Dutch government collapses as far-right leader pulls party out of coalition
- Anti-immigrant leader quits Dutch cabinet, toppling government
- Polder model – Wikipedia
- Netherlands Elections Overview – Election Guide
ご感想やご相談などありましたら、
こちらのお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
「さちこの無職日記」を読んでくださってありがとうございます。
よければ、また遊びにきてくださいね!